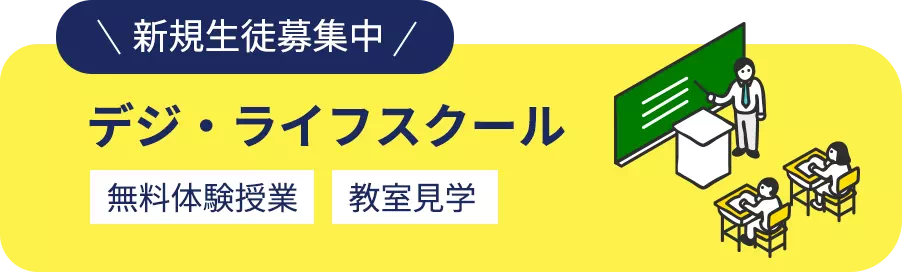column
デジ・ライフコラム
INDEX
現代人に贈る「心と体のメンテナンス」術
4月、新年度が始まり、職場や学校で新たな人間関係や業務がスタートします。新しい環境への適応に全力を注いだあとにやってくる5月――そこに待っているのが、いわゆる「五月病」です。
この五月病、医学的な病名ではありませんが、軽度のうつ症状や倦怠感、無気力、食欲不振、不眠といったさまざまな不調が見られ、多くの人が何となく心当たりを感じているはずです。
特に在宅勤務やフリーランスといった「パソコン中心」の生活を送る現代人にとって、知らず知らずのうちに心身のバランスを崩してしまう危険があります。
では、私たちはどうパソコンと付き合っていけば、五月病を予防できるのでしょうか?
パソコンが五月病の引き金になる?
まず、パソコン中心の生活が五月病とどう関係しているのかを見てみましょう。
1. 運動不足と日照不足

長時間のパソコン作業は、当然ながら身体の動きが制限されます。特に在宅勤務では通勤すらなくなり、気が付けば1日1000歩も歩いていないということも…。
運動不足が続くと、脳内のセロトニン(幸せホルモン)の分泌が低下し、気分が落ち込みやすくなります。
さらに、室内にこもりがちになると日光に当たる機会も減り、体内時計が乱れて睡眠の質が下がるなど、悪循環が生まれます。
2. 人との交流の減少

オンラインミーティングは便利ですが、対面での雑談やアイコンタクトのような微細なコミュニケーションは激減します。
孤独感や疎外感が積もることで、知らず知らずのうちにメンタルが摩耗してしまうのです。
3. 情報過多と脳の疲弊

インターネットは有益な情報の宝庫ですが、逆に言えば終わりのない情報の海。仕事中もプライベートでも常に画面から流れ込むニュース、SNSの通知、メール…。
脳は絶え間なく処理を求められ、気づかぬうちに“情報疲れ”を起こしています。
五月病を防ぐパソコンとの「健全な関係」
では、こうしたリスクを避けるために、パソコンをどう活用すればよいのでしょうか。
以下に具体的な方法を紹介します。
1. ポモドーロ・テクニック

作業にリズムを集中と休憩を意識的に切り替えることで、脳への負担を軽減できます。
たとえば「25分作業+5分休憩」を1セットとするポモドーロ・テクニック。これを1日4~5セット実施するだけでも、疲れが溜まりにくく、気分も安定します。
専用のタイマーアプリも多数あり、画面上で進捗管理も可能です。
2. スタンディングデスクや簡易昇降台の活用

同じ姿勢が長時間続くと、血流が滞り、肩こりや腰痛の原因になります。できれば1日の中で数回は立ったまま作業できる時間を設けましょう。
スタンディングデスクを購入するのが難しい場合でも、箱や台を活用してノートパソコンの高さを調整すれば即席スタンドが完成。
立ち作業と座り作業を交互に行うことで、気分の切り替えにも効果的です。
3. 「仮想通勤」で生活リズムを守る

在宅勤務やパソコン作業が中心の生活では、外に出る用事が極端に減ります。
そこでおすすめなのが「仮想通勤」。朝の始業前や昼休みに、あえて15分ほど散歩する習慣を作るのです。
スマートフォンの歩数計や天気アプリを使い、日々の変化を感じながら歩くと、自然と気持ちが晴れていきます。
これがセロトニンの分泌を促し、うつ傾向の予防にもつながります。
4. ブルーライトと上手に付き合う

パソコンやスマホのブルーライトは、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を妨げます。
夜にパソコン作業をする際は、画面をナイトモードにしたり、ブルーライトカットの眼鏡を使うなどの工夫が必要です。
また、「夜10時以降はスマホを見ない」「就寝1時間前は画面から離れる」など、ルールを決めることも効果的。
とにかくぐっすり眠ることが、五月病の最大の予防策です。
5. デジタル日記で感情の可視化

パソコンをポジティブなメンタルケアツールとして活用する方法もあります。
たとえば、毎日の終わりに「今日よかったことを3つ書く」などの簡単な日記をつけることで、心の状態を客観視することができます。
NotionやEvernote、OneNoteといったツールを使えば、スマホとも連携できて便利。
数週間続けるだけで、自分の感情の波に気づき、自己理解が深まります。
「パソコンを切る時間」こそ最大の養生時間

最後に大切なのは、「パソコンから離れる時間」を意識して作ることです。
便利な道具だからこそ、四六時中付き合っていると、私たちは「情報に追いかけられる側」になってしまいます。
ときには、電源を切り、外の空気を吸い、人と話し、趣味に没頭する。そんなアナログな時間が、心と体のリズムを整えてくれます。
五月病を予防するためには、単に「休む」ことだけでなく、「どう休むか」「どう働くか」が大事。
パソコンはあなたの敵ではありません。うまく付き合えば、むしろ心の健康を支える大切な味方になってくれるのです。
おわりに

五月病は誰にでも起こりうる「心の疲れのサイン」です。だからこそ、無理に「頑張りすぎない」こと、そしてデジタルツールと上手に付き合う知恵が求められます。
パソコンという現代人の相棒と、よりよい関係を築くこと――それが、これからの働き方・生き方における最良の処方箋になるかもしれません。